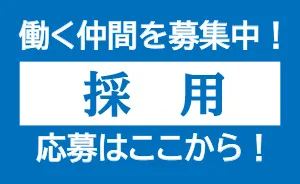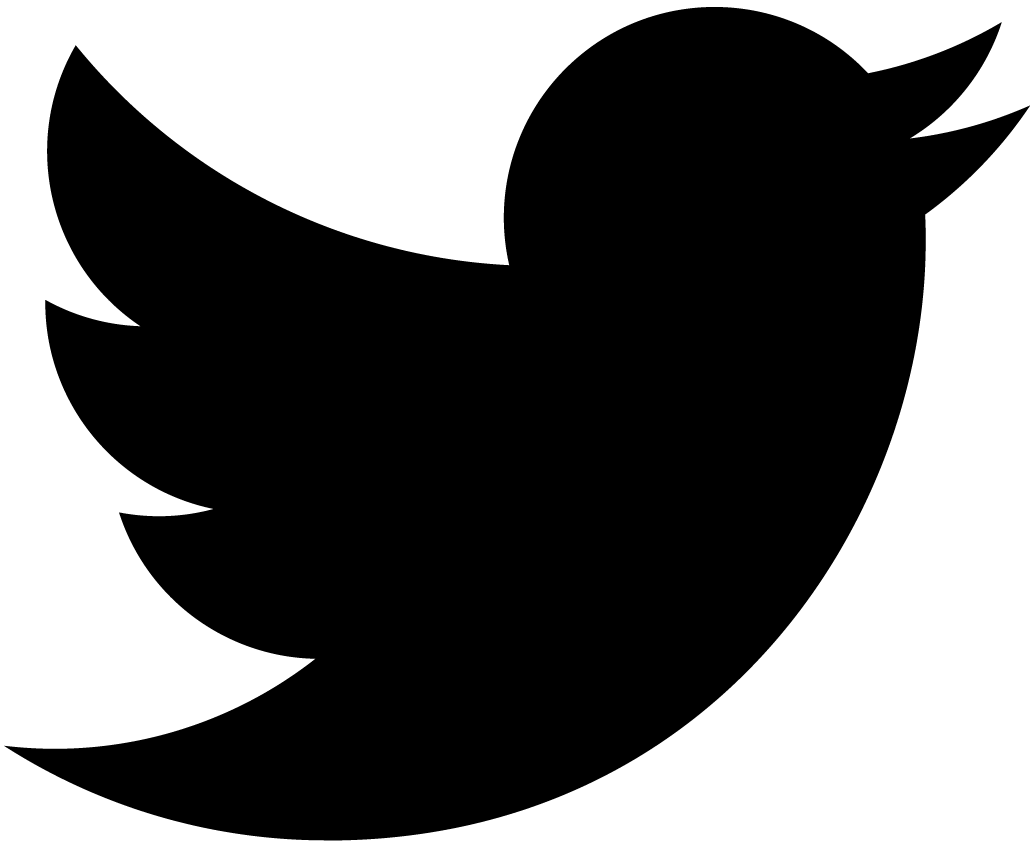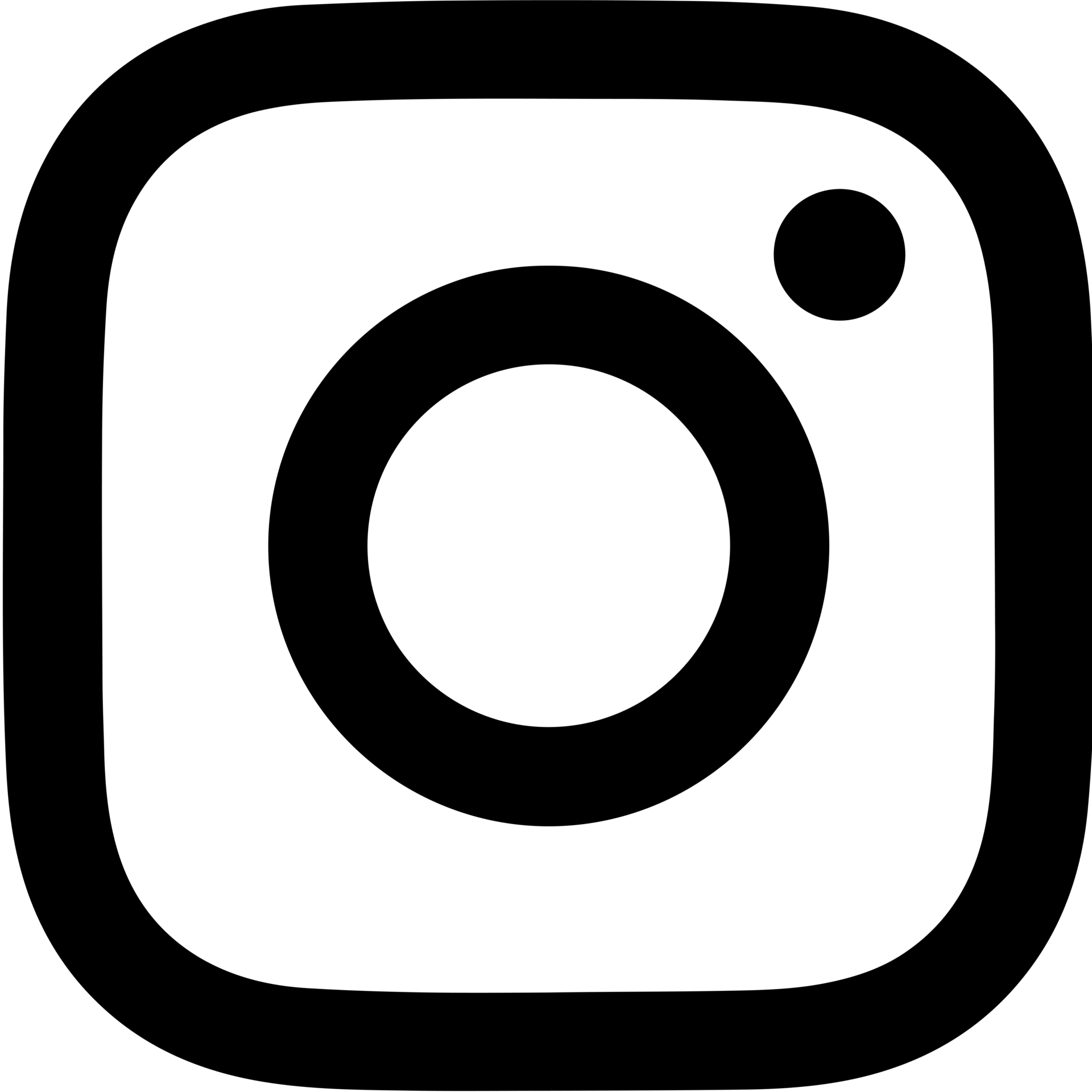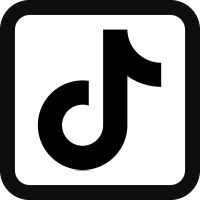警備員の研修は必要?内容についても併せて紹介
2025.04.03 Thu
警備員として働くためには、所定の研修(教育)を受ける必要があります。
もし研修を受けなかった場合は、警備業法違反となり警備員として働くことはできません。
研修には新任向けと現任向けの2種類があり、それぞれ受講対象者が異なります。
本記事では、警備員の研修の種類や内容について詳しくご紹介します。
研修内容や時間が変わりますので、違いを明確にお伝えいたします。
研修の種類
警備員として働くためには不可欠な研修ですが、新任教育と現任教育に分けることができます。
どちらを受講するかは、一人ひとりの経験によって異なります。
警備員未経験者の方や、ある程度ブランクがある方は新任教育を受けることになります。
新任教育はさまざまなカリキュラムで構成されており、法定で定められている現任教育と比較すると研修時間が長めです。
法定で規定された研修時間を受けると、現場で警備業務に従事することができます。
現役の警備員の方を対象とした研修が現任教育です。
こちらは新任教育と比べて研修時間は短く、基本の確認を中心としたカリキュラムになっています。
ただし、現任教育は警備業法で規定されているため、一定期間ごとに研修を受ける必要があります。
もし現任教育を怠ると、現場で警備業務に従事できなくなってしまいます。
教育懈怠とみなされ、警備業法違反となるので注意が必要です。
新人警備員向けの「新任教育」
2つある研修のうち、警備業務に従事するために欠かせない研修が新任教育です。
新任教育とは、これから警備員として働くために必要な知識を学ぶための研修のことです。
一般企業における新人研修・新人教育のことで、警備業の基本を一から学んでいただきます。
警備の業務は安全・安心に関わるため、非常に重要度の高い研修となっています。
新任教育は警備業法で義務化されており、対象者は必ず受講しなくてはいけません。
そのため、実際に警備員として働き始めるのは新任教育後となります。
新任教育は「基本教育」と「業務別教育」の2種類があります。
いずれも座学を中心としていますが、礼式と呼ばれる実技や訓練も実施されます。
法令や警備員の基礎を学ぶ「基本教育」
警備員として働くにあたって、覚えておくべき基本を学ぶためのものが基本教育です。
基本教育は、主に警備業に関する法令や知識などの習得を中心とした研修のことを言います。
警備員としての心構えや、安全を確保するための技術についても学ぶことが可能です。
事故が発生した時の対処法や救護用具の使用方法など、実務で役立つ知識も身に付けることができます。
基本教育は、警備員に共通した事柄の学習が中心です。
主な研修はテキストや映像などの教材を用いた座学ですが、必要に応じて礼式も実施されます。
礼式では、敬礼の方法や掛け声などの基本動作について学びます。
警備業務別に異なる内容を学ぶ「業務別教育」
基本教育が完了した後に実施される研修が業務別教育です。
業務別教育は、警備業務の種類に合わせて行われる研修です。
警備業には1号業務から4号業務までありますが、業務別教育ではそれぞれに特化した内容を学びます。
- 1号業務の場合:ビルや商業施設などで業務を行う際に必要な知識・技術を学習
- 2号業務の場合:現場での交通誘導や雑踏警備の方法を学習
- 3号業務の場合:貴重品輸送や危険物運搬に関わる内容を学習
- 4号業務の場合:対象者の身辺警護に必要な知識・技術を学習
業務別教育は、警備業務の種類によって研修内容が大きく異なります。
必要に応じて実地で教育を実施することもあります。
株式会社WAKABAでは上記の2号業務の内容を学習していただくことになります。
新任教育の対象者
新任教育は、これから初めて警備員として働く方を対象としています。
そのため、警備員が未経験の方であっても、新任教育で基礎知識・技術を磨くことが可能です。
警備員としての経験がある方も新任教育の対象となるケースがあります。
新任教育が免除されるのは、主に警備業務検定の1級または2級の有資格者です。
ただし、警備員の経験がある方については、過去と同一の警備業務に就く場合は研修時間が短くなります。
新任教育の研修時間について
新任教育の研修時間は、経験の有無によって異なります。
警備員の経験がない方の場合は、基本教育・業務別教育合わせて20時間以上の新任教育が必要です。
株式会社WAKABAでは3日間の新任教育の研修時間を設けております
警備員の経験者については、同一の警備業務に就く場合で7時間以上の新任教育が求められます。
新任教育のメリット
新任教育を受けるメリットは、警備業務を始める前に基礎知識や技術を身に付けられる点にあります。
警備員の仕事は責任重大で、その時の状況に合わせた臨機応変な対応が求められます。
新任教育で事故やインシデント発生時の対処法について学んでおけば、もしもの時でも適切に対応することができます。
事前に業務内容を把握できることもメリットの一つです。
警備業務を始める前に心構えができる他、想像と実際の業務のギャップを埋めることが可能です。
警備業務従事者を対象とした「現任教育」
現在警備業務に従事している方を対象とした研修を「現任教育」と言います。
警備業法では現任教育の実施が義務化されているため、対象者は必ず研修を受ける必要があります。
新任教育と同じく「基本教育」と「業務別教育」に分けられています。
基本原則を再確認する「基本教育」
現任教育における基本教育は、主に警備員としての基本を再確認するための研修です。
警備業務の以下の内容について振り返り、業務のクオリティを維持することを主な目的としています。
- 警備業務の基本原則
- 警備業法など関連法令
- 事故発生時の対処法や連絡・措置について
適切に警備業務へ従事できるように、これらについて座学などで再確認できます。
警備業法が改正された時は、改正内容・ポイントについて学ぶことが可能です。
スキル向上・維持を目的とした「業務別教育」
もう一方の業務別教育は、警備業務におけるスキルの向上や維持を図るためのものです。
新任教育ではスキルや技術の習得が主な役割でしたが、現任教育では少々目的が異なっています。
現任教育における業務別教育は、警備業務の種類によって研修内容が変わります。
ただ、基本的な内容は普段の警備業務に関わるもので、新任研修とあまり変わりません。
例えば1号業務の場合、施設の巡回や監視、不審物・不審者を発見した時の対処法などについて再確認できます。
現任教育の頻度・研修時間について
現任教育の実施頻度は警備会社によって異なります。
ただ、1年間で所定時間以上の研修が義務化されていますので、最低でも年1回は実施しなくてはいけません。
もしトータルの研修時間が警備業法で定められた基準を下回ると、教育懈怠とみなされる可能性があります。
現任教育の必要時間は一般警備員で10時間以上と規定されています。
警備業務検定2級の合格者は6時間以上、1級の合格者は現任教育が免除されます。
ただし、当該警備以外に就く時は1級・2級合格者ともに6時間以上の現任教育が必要です。
もし研修を受けなかったらどうなる?
警備員の研修を受けなかった場合は、警備員として働くことができません。
新たに働き始める時はもちろん、警備員の仕事を続けるためにも必要です。
警備業法では、適切な警備業務を遂行させるために必要な研修の実施を義務付けています。
警備員に対して基本的な業務を覚えてもらったり、業務に合わせたスキルを磨いたりするためです。
そのため、警備員として働くためには研修の受講が必要不可欠です。
研修を受けなかったときは警備業法違反に問われてしまうなど、ペナルティが課せられる恐れもあります。
警備会社が営業停止処分になることがある他、警備員自身も処罰される可能性があるので注意が必要です。
まとめ
警備員として働くためには、警備業法に基づいた所定の研修を受ける必要があります。
研修は新任研修と現任研修の2種類があり、それぞれ対象者が異なります。
研修時間も法令で定められていますので、基準を満たせるようにすることが大切です。