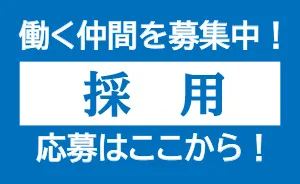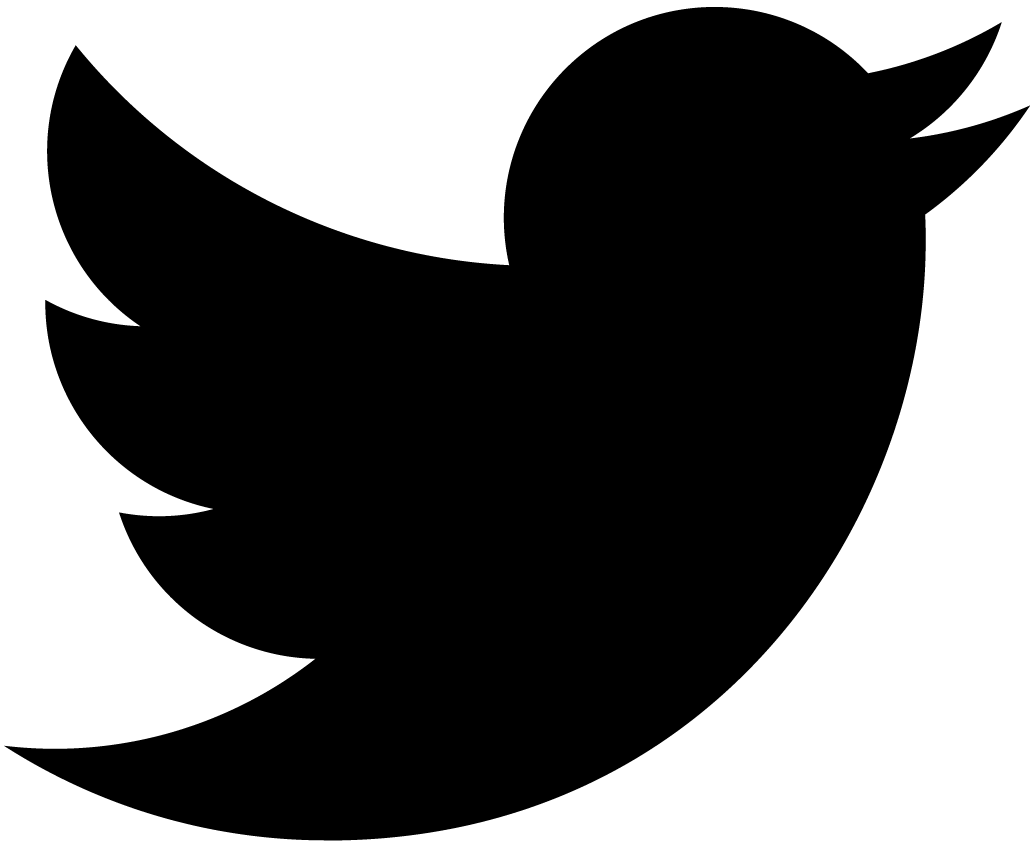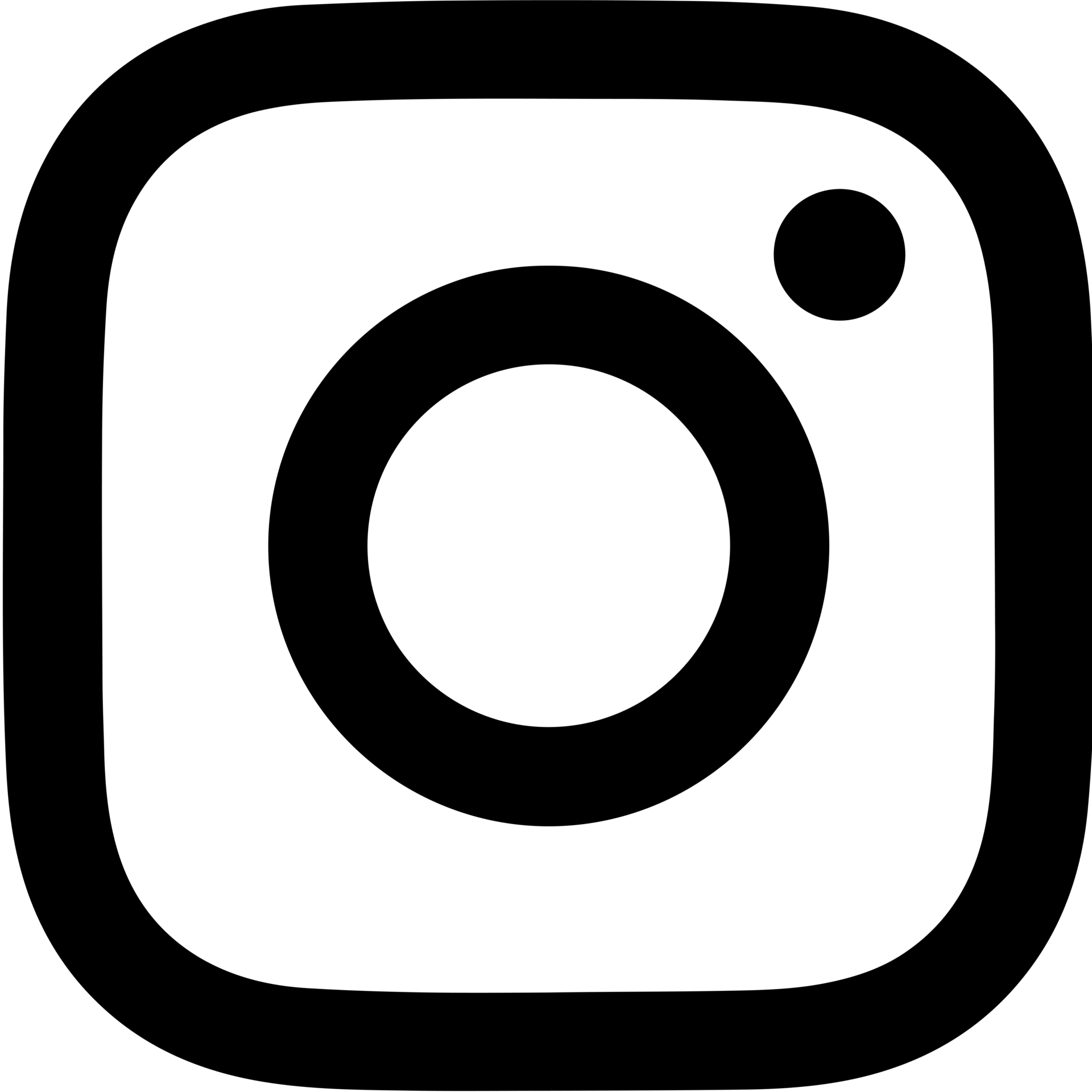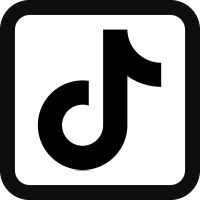警備業法とは?
2025.02.05 Wed
警備業法は、警備業に関する規則や制限などについてまとめた法律のことをいいます。
主に警備会社を対象とした法律ですが、警備員として働く場合も同法の遵守に努める必要があります。
本記事では、警備業法の特徴や目的の他、警備業務の種類・違いを詳しく解説いたします。
警備業法とは?
警備業法は、警備会社の運営に関して定められた法律です。
警備業を営むにあたって守るべき規則や、業務の遂行などについて細かくまとめられています。
警備業法の内容は多岐にわたりますが、以下では主な内容をご紹介します。
警備業務の健全な運営に関する規定
警備業法では、日本における警備業の健全な運営を確保するための規定を定めています。
主に警備会社や警備員が遵守すべき義務とその違反に対する罰則について以下の内容が盛り込まれています。
- 基本的業務について
- 違反行為と禁止事項について
- 警備員の資格や制限について
- 上記に違反した時の罰則について
基本的業務は、警備会社・警備員の主な業務を定めたものです。
警備会社は警備業務を行う際に法令を遵守し、かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
警備業務を通じて知り得た情報や秘密を漏らしてはいけないという守秘義務もあります。
警備会社や警備員が業務の中で違法行為を行った場合、その行為に対して厳しい罰則が科されます。
たとえば、虚偽の報告や不正な手段による利益の取得が禁止されています。
警備員の資格・制限についても規定されています。
警備員として働く際には資格は不要ですが、欠格事由に該当するかたは働くことができません。
そうした警備員の制限については、警備業法の中で細かく決められています。
これらに違反した際の罰則も明記されています。
中には重い罰則もあるため、違反しないように注意が必要です。
警備業務の従事者の配置や教育に関する規定
警備業法は、警備業務の従事者の適正な配置と教育についても定めています。
以下のように、主に警備会社が適切な人材を確保し、必要な知識と技能を持って業務を遂行できるようにすることを目的としています。
- 人材の適正な配置について
- 教育義務について
- 教育計画の策定や記録について
警備会社は、警備業務の従事者を適正に配置しなければなりません。
業務の内容はもちろん従事者の経験も考慮して配置する必要があります。
警備会社には、警備員が業務に必要な知識と技能の習得に必要な教育・訓練の実施も求められます。
教育・訓練では警備員の基本スキルを身に付けていただくだけでなく、法令の遵守や緊急対応なども指導する必要があります。
一方、警備会社は教育計画も策定しなくてはいけません。
教育計画は主に警備員の能力や業務のクオリティ向上を目的とした体系的なものが必要です。
実施した教育・訓練に関する内容については、適切に管理しなくてはいけません。
場合によっては、関係機関へ速やかに報告できるよう体制を整備する必要があります。
警備会社・警備員に関する監督と規制について
警備業法では、警備会社および警備員に関する監督と規制も規定しています。
同法の監督や規制は、警察や関係当局の監督権限を明確にして必要な措置を講じることを目的としています。
警備業の安全性や信頼性に関する内容が盛り込まれており、適正な運営を確保するために必要なものです。
主に規定されている内容は次の通りです。
- 関係機関による監督について
- 業務に関する報告について
- 改善や是正指示について
警察や関係機関は、警備会社や警備員の業務が法令に基づいて適正に行われているかを監督する権限を持っています。
たとえば、業務の実施状況の確認や現地調査などが含まれます。
警察や関係当局から報告を求められた場合、警備会社や警備員は業務に関する報告を実施しなくてはいけません。
業務についての報告は、警備業の透明性確保と適正な運営を目的として定められています。
もし法令違反が見つかった時や欠陥が発見された場合は、警察や関係当局が改善命令を出すことができます。
具体的には警備会社や警備員について違反行為を是正したり、業務改善を指示したりなどです。
是正・改善に従わなかった場合、業務や営業停止命令を出される可能性もあります。
もし停止命令が出された時は、一定期間警備業務の遂行を禁止されます。
警備業法は警備員にとっても無関係ではない
警備業法は警備業を健全に運営し、信頼性を確保するために必要な事項をまとめています。
そのほとんどは警備会社に関係したものですが、働く警備員にとっても無関係ではありません。
もし警備業法に違反してしまった場合は、自分だけでなく働いている警備会社にもペナルティが課せられるリスクがあります。
違反した内容にもよりますが、罰則は重いので注意が必要です。
警備業法に抵触する主な違反行為とは
警備業法はルールが細かく定められていますが、以下に該当する行為は同法違反とみなされる可能性があります。
- 他社に警備員として派遣された・他社から警備員を派遣してもらった
- 警備業法で規定された教育・訓練を実施しなかった
- 虚偽の教育記録・報告を行った
特に多いのは警備員の派遣に関する違反です。
警備業務は指揮命令権が警備会社にあるため、警備員の派遣は厳しく制限されています。
請負という形であれば問題ありませんが、派遣となると罰則が課される可能性があるのです。
そのため、他社に派遣された(他社から派遣してもらった)場合は警備業法に抵触する恐れがあります。
警備会社が警備業法で定められた教育・訓練を実施しなかった時も同様です。
これは教育懈怠と呼ばれており、警備員に適切な教育を受けさせず業務に従事させることを言います。
警備会社で働く場合、教育環境がしっかりしているところを選ぶことが重要です。
警備員の教育について虚偽があった時も警備業法違反となります。
たとえば教育を実施したと嘘の記録を行ったり、関係機関へ報告したりする行為が該当します。
虚偽の記録などに関する罰則は非常に重く、警備会社に立入検査が入るケースもあります。
警備業法における警備業務の種類・違い
警備業法では、警備業務の内容に合わせて1号から4号まで細分化しています。
警備する場所や業務内容が大きく変わるため、違いを把握することが大切です。
ここからは、警備業務の種類や違いについて詳しく解説します。
1号業務(施設警備業務)
ビルやオフィス、工場などの施設内での警備を担当するのが1号業務です。
該当施設で以下の役割を担います。
- 施設内の巡回
- 人物の出入りの管理
- 監視カメラのチェック
- 不審者・不審物の発見と対応
施設の安全に大きく関わるのが1号業務と言っても過言ではありません。
施設内の安全を確保するために、警備員は24時間体制で勤務することもあります。
火災や地震などの緊急時には避難誘導にも携わります。
1号業務は多くの場所で求められており、日常的な安全管理で重要な役割を担っています。
2号業務(交通誘導警備業務)
工事現場やイベント会場などでの交通整理・誘導に携わるのが2号業務です。
主に工事車両や一般車両が安全に通行できるよう指示を出したり、歩行者の安全を確保したりする役割を担っています。
屋外での業務が中心のため、季節によっては体力が求められる仕事です。
2号業務は交通誘導や雑踏警備が中心ですが、事故を未然に防ぐための迅速な対応が求められます。
特に交通量の多い場所や大規模なイベント会場では、参加者の安全を確保し、混雑を避けるための誘導が必要です。
3号業務(貴重品運搬警備業務)
現金や貴金属、美術品などの高価な物品の輸送を担当するのが3号業務です。
3号業務の警備員は専用の車両や器具を使用し、輸送中の安全を確保する役割を担っています。
特に金融機関や貴金属取扱業者などで必要とされる警備業務です。
3号業務では、貴重品の運搬経路や時間などが厳重に管理されているため、情報の漏えいを防ぐための細心の注意が求められます。
トラブルが発生した時は状況を見極め、適切な対応をする必要があります。
4号業務(身辺警備業務)
特定の人物の身辺警護にあたるのが4号業務です。
いわゆるボディガードで、VIPや著名人を対象に身辺の警護を行います。
4号業務では、警備対象者の安全を確保するために緻密な警備計画を立てることが求められます。
リスクに対する適切な評価を実施し、状況に合わせて対応するスキルも必要です。
特に不審者や危険から対象者を守るために、高度なスキルと迅速な判断力が求められます。
こうした事態に備えるためには、平時においても入念な訓練と準備をしておく必要があります。
まとめ
警備業法は、警備業を営むために必要な規制やルールを細かく規定した法律です。
警備会社はもちろん、警備員が遵守すべき内容も盛り込まれています。
同法では警備業務を1号から4号まで細分化しています。
種類によって警備業務の内容が異なるため、違いをしっかり覚えることをおすすめいたします。