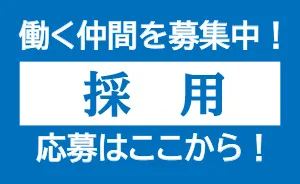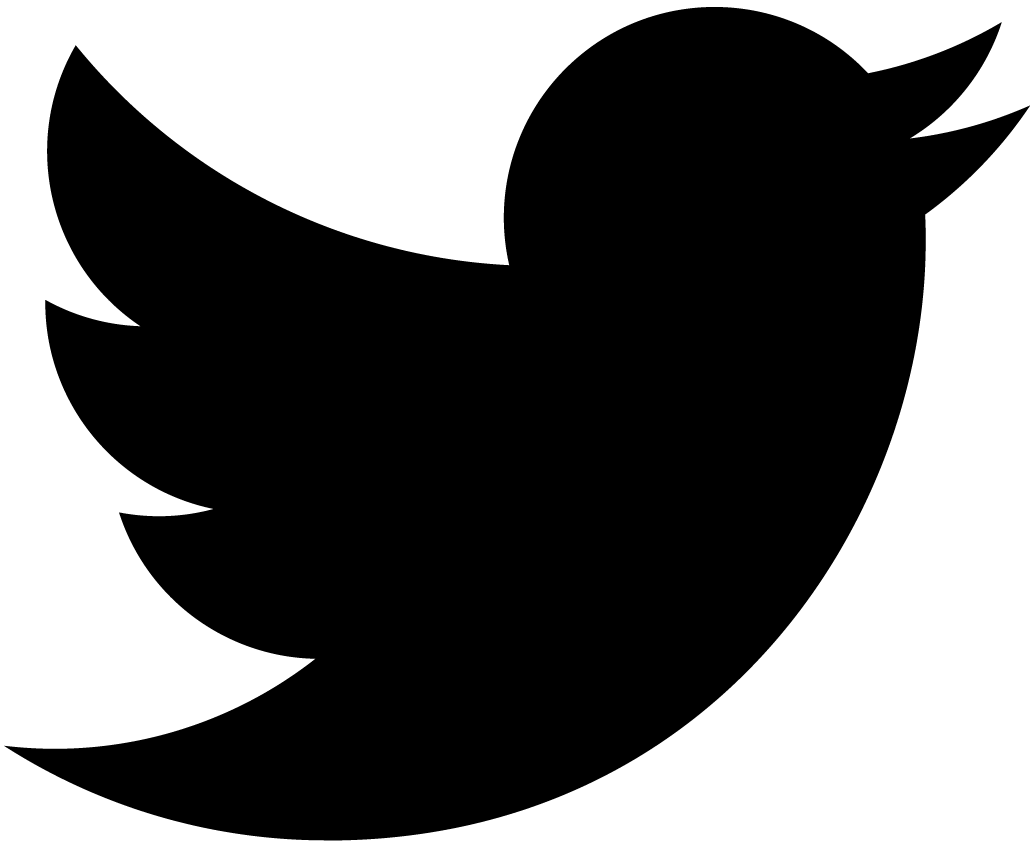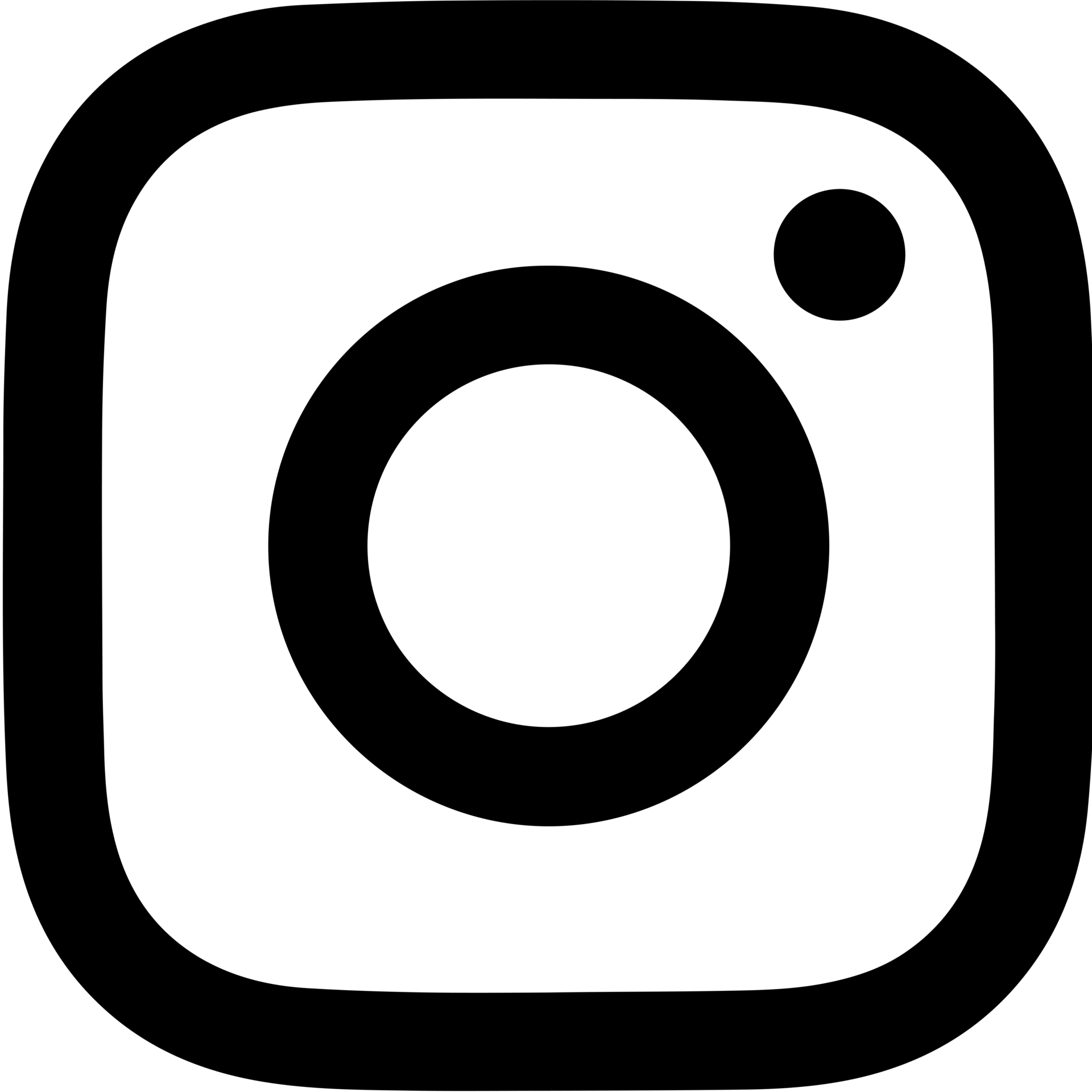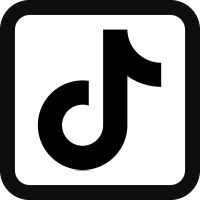交通誘導警備と雑踏警備の違いとは?
2025.08.08 Fri
交通誘導警備や雑踏警備は、車両や歩行者の安全を確保し、円滑な交通をサポートするために必要な警備業務です。
どちらも警備業法における2号業務に分類されており、基本的な業務内容には違いがありません。
交通誘導警備・雑踏警備では主な役割や配属先などが異なっています。
似通っている面も多いですが、細かな部分は違いが多いので注意が必要です。
本記事では交通誘導警備と雑踏警備の主な違いを解説します。
交通誘導警備とは?
工事現場の入口や駐車場などに立ち、歩行者・車両を誘導するのが交通誘導警備です。
車両などの円滑な通行をサポートし、事故を未然に防ぐことが主な役割となっています。
交通誘導警備の主な仕事内容
交通誘導警備の主な仕事は次の通りです。
- 道路での車両の交通誘導
- 工事現場での工事車両の誘導
- 商業施設での歩行者・車両誘導
- 事故やトラブル発生時の対処
道路や工事現場での車両誘導のほか、商業施設で歩行者などの誘導に従事します。
また、万が一事故やトラブルが発生した際は、状況に合わせた適切な対処もおこないます。
交通誘導警備に携わるには
交通誘導警備業務に携わる場合、2号業務を手がける警備会社に所属する必要があります。
2号業務は多くの警備会社がおこなっているため、警備会社探しは決して難しくありません。
交通誘導警備業務を始める際は、警備業法で定められた研修・教育を受ける必要があります。
研修は未経験者向きの新任教育と経験者向きの現任教育に分けられます。
新任教育は座学や訓練を中心に数十時間おこなわれます。
対する現任教育は、新任教育より時間が少ないものの、該当する警備業務に従事する全員が受講する必要があります。
未経験者の場合、新任教育後に交通誘導警備の業務を始めることが可能です。
以後は定期的に現任教育を受けることで、現場に関わらず交通誘導警備に携われます。
交通誘導警備に必要な資格・スキルは?
交通誘導警備業務を始めるにあたって必要な資格はありません。
円滑に業務を進めるためには、現場の状況を迅速に判断するスキルや適切に誘導するスキルなどが求められます。
しかし、これらのスキルは警備会社が実施する各種教育・研修で身に付けられます。
そのため、警備業務の未経験者であってもチャレンジすることが可能です。
雑踏警備とは?
交通誘導警備と同じ2号業務に当てはまるのが雑踏警備です。
通路に立ち、歩行者がスムーズに移動できるよう誘導する役割を持っています。
一方で交通誘導とは仕事内容が異なるため、違いをしっかり把握することが大切です。
雑踏警備の主な仕事内容
雑踏警備の主な仕事内容は次の通りです。
- 列が乱れないよう来場者を誘導する
- 来場者の手荷物検査をおこなう
- 不審者がいないか区域内を監視・巡回する
- 不審物がないか区域内を巡回する
- 来場者の案内や問い合わせへの対応
- 事故・事件発生時の対応
雑踏警備の仕事はイベント会場で来場者を誘導したり、手荷物検査をおこなったりすることがあります。
必要に応じて担当の区域内を巡回し、不審者や不審物の監視やチェックをおこないます。
他にも来場者の案内・問い合わせへの対応や、事故発生時の対応も雑踏警備の重要な仕事です。
このように雑踏警備は交通誘導警備と比較して役割や仕事内容が多岐にわたります。
雑踏警備に携わるには
雑踏警備に携わる場合、2号業務に対応した警備会社に採用される必要があります。
採用された後は、警備業法で定められた新任教育を受けることで業務を開始できます。
この流れは交通誘導警備はもちろん、他の警備業務でも変わりません。
雑踏警備の仕事は資格が不要なため、教育を受ければ誰でも始めることが可能です。
ただ、交通誘導警備と比べて多くの仕事をこなすことから、様々なスキルが求められます。
本格的に雑踏警備業務へ携わりたい場合、資格の取得を目指してみるのもおすすめです。
交通誘導警備と雑踏警備はどちらも「2号業務」にあたる
交通誘導警備と雑踏警備の共通点が警備業法での取り扱いです。
警備業法では、内容によって警備業務を区分しており、交通誘導警備と雑踏警備は2号業務に分類されています。
2号業務は、人や車両が集まる場所での安全確保に務める警備業務です。
主な業務は人や車両の誘導ですが、その時の状況に合わせた対応が求められます。
警備員の業務は2号業務の他にも複数の業務があり、それぞれ役割や配属先、業務内容などが異なっています。
交通誘導警備と雑踏警備の違い
交通誘導警備と雑踏警備は、一見似ているようで多くの違いがみられます。
配属先の違い
交通誘導警備と雑踏警備の違いとして、まず挙げられるのが配属先です。
交通誘導警備は、主に以下の場所で警備業務に従事します。
- 工事現場
- イベント会場
- ショッピングセンターなど商業施設の駐車場
特に多くみられるのは工事現場で、場合によってはイベント会場や商業施設で交通誘導をおこないます。
一方の雑踏警備は、主にイベント会場で警備業務に携わります。
たとえば以下のようなイベントが開催される場合、雑踏警備として現場に赴くことがあります。
- 音楽ライブやフェス
- 花火大会など大型イベント
- 展示会
基本的に人が多く集まる場所や、一度にたくさんの人が訪れる場所で警備業務に従事します。
役割や業務範囲の違い
交通誘導警備と雑踏警備は、役割や業務範囲にも違いがみられます。
交通誘導警備は、文字通り人や車両などを誘導することが主な業務となっています。
道路や通路で人・車両がスムーズに通行できるように、適切に誘導して安全を確保することが警備員の役割です。
交通誘導の場合、工事現場では車両の誘導が中心です。
商業施設やイベント会場などでは、車両だけでなく人の誘導もおこないます。
雑踏警備の主な役割は、イベント会場を訪れる来場者の安全確保です。
交通誘導警備と似ていますが、主に以下の業務をこなします。
- 来場者の出入り口への誘導
- 不審者・不審物への警戒
- 来場者の問い合わせ対応
- 迷子の保護や対応
- その他トラブルへの対応
来場者の誘導はもちろん、不審者・不審物の警戒や発見も雑踏警備の役目です。
来場者に道案内をしたり、迷子やトラブルへ対応したりなどさまざまな業務をこなします。
従事期間の違い
交通誘導警備と雑踏警備は従事期間も異なります。
交通誘導警備は、工事現場などで一定期間警備業務に携わるのが一般的です。
期間は現場によって異なるものの、通常は継続的に交通誘導をおこないます。
そのため、同じ現場で長期間業務に従事するケースも珍しくはありません。
一方雑踏警備はイベント会場などで一定期間警備業務に従事します。
イベントの開催期間は短いことが多いため、短期間で終わるケースも少なくありません。
交通誘導警備とは違い、さまざまな現場で警備業務にあたるのが一般的です。
資格にも違いがみられる
交通誘導警備と雑踏警備は資格も異なります。
警備業に関する資格は警備業法で定められており、合わせて以下の6種類の資格があります。
- 施設警備業務
- 空港保安警備業務
- 交通誘導警備業務
- 雑踏警備業務
- 核燃料物質等危険物運搬警備業務
- 貴重品運搬警備業務
交通誘導警備・雑踏警備は、別々の資格が定められています。
いずれも1級と2級がありますが、取得の難易度がかなり異なります。
警備員の仕事は資格がなくても始めることが可能です。
資格を取得すれば交通誘導警備・雑踏警備に関する高度な知識・スキルを身に付けられます。
まとめ
交通誘導警備と雑踏警備は、いずれも警備業法における2号業務に該当します。
仕事内容や配属先、業務の従事期間などは大きく異なるのが実情です。
交通誘導と交通整理も間違えやすいですが、後者は警察官のみがおこなえます。
主な役割が異なるため、混同しないように注意が必要です。