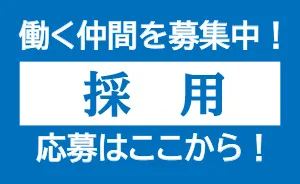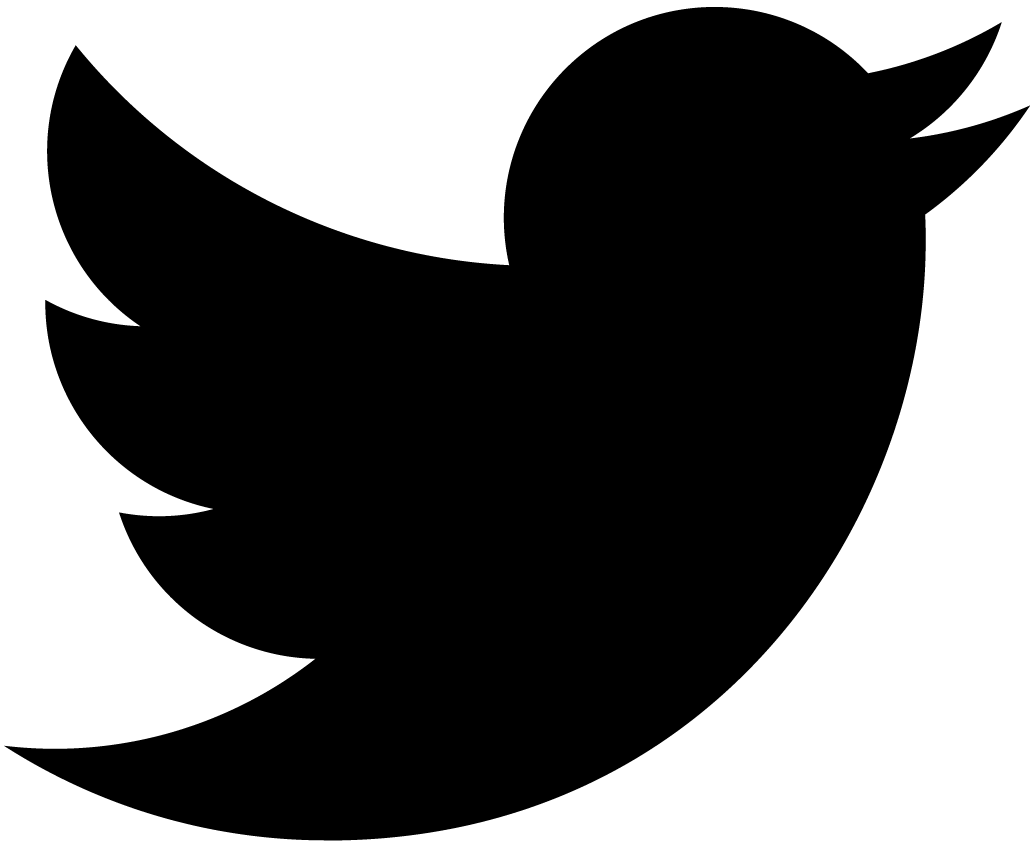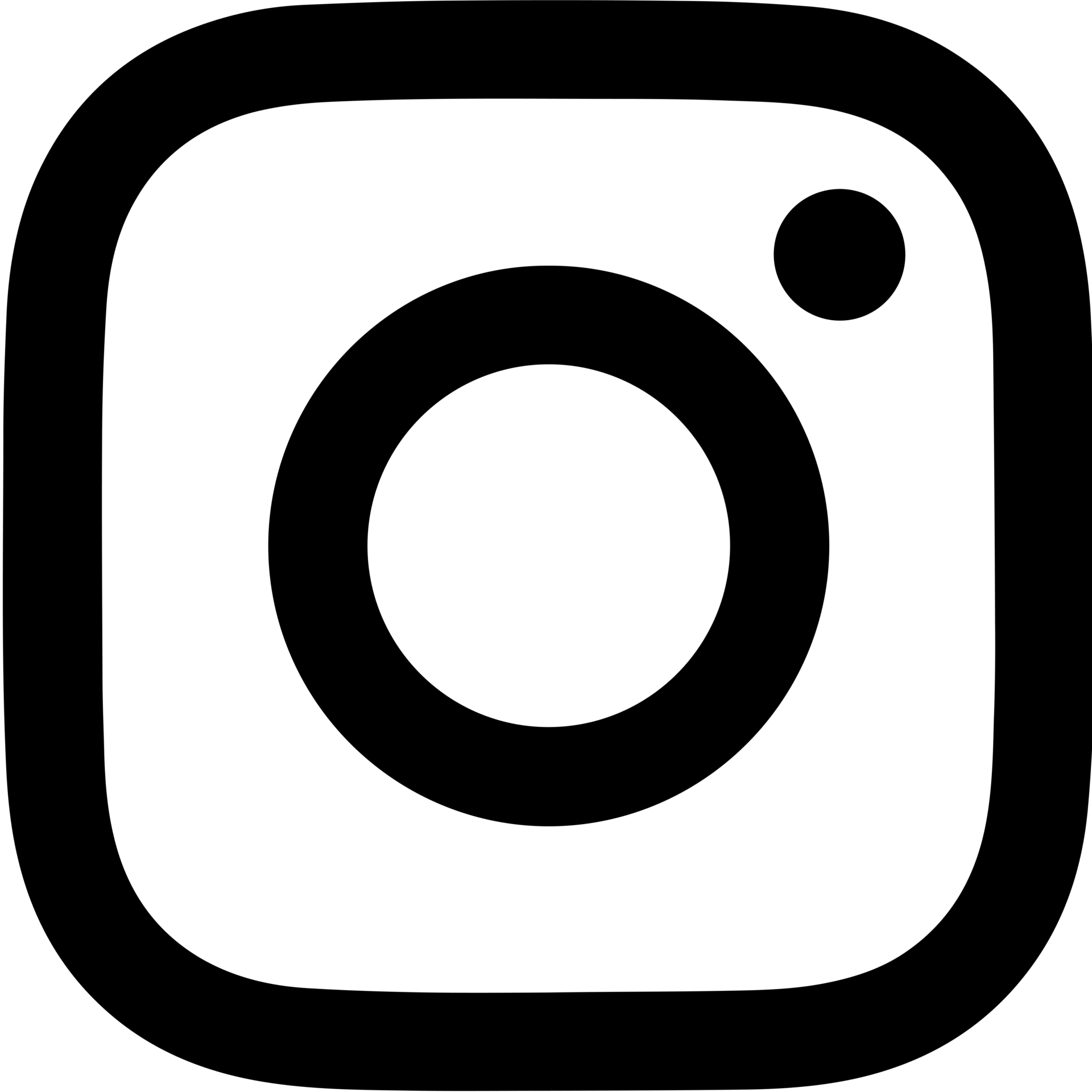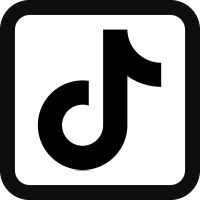守衛と警備員の違いとは?
2025.05.13 Tue
警備員と似た職種や業種は多数ありますが、守衛もその中のひとつです。
守衛は施設の警備にあたる職種で、出入りする利用者・来訪者の監視や応対を行っています。
警備員と守衛の仕事は一見すると同じに見えますが、基本的には異なる職種です。
法律や所属など違う点も多数ありますので、間違えないように注意する必要があります。
本記事では、警備員と守衛の違いやそれぞれの仕事内容・配属先などについて解説します。
守衛と警備員の違い
警備員と守衛の主な違いは次の4つです。
- 雇用主(所属)
- 警備・警護対象
- 法律の規制
- 研修の有無(義務かどうかも含め)
それぞれの違いについて詳しく解説します。
雇用主(所属)が異なる
警備員と守衛の違いとして、まず挙げられるのが雇用主です。
基本的に警備員と守衛は役割が異なりますので、所属する会社に違いがみられます。
警備員はさまざまな現場で警備にあたる職種で、雇用主は警備会社になります。
警備会社で必要な研修・教育を受け、指定された現場で警備業務にあたります。
一方の守衛は、警備にあたる対象施設の運営会社・組織が主な雇用主です。
たとえば博物館の守衛の場合、その博物館を運営する会社が雇用主であり、守衛も同館の所属となります。
そのため、守衛は雇用主が運営する施設の警備や来訪者の応対が主な役割です。
警備員は雇用主が警備会社のため、給与の支払いはもちろん、福利厚生・待遇も警備会社のものが適用されます。
対する守衛は雇用主である施設の運営会社が給与を支払い、福利厚生などを提供しています。
警備・警護にあたる対象が違う
警備や警護対象にも違いがみられます。
警備員は1号警備業務から4号警備業務に分かれており、以下のように警備する対象や内容が異なっています。
- 1号警備業務:施設警備
- 2号警備業務:交通誘導および雑踏警備
- 3号警備業務:貴重品や危険物の運搬および警備
- 4号警備業務:身辺警護(ボディガード)
このように従事する業務によって警備内容や警護する対象が大きく変わるのが特徴です。
知識やスキル、経験などに合わせてさまざまな警備業務に就きます。
一方の守衛は、勤務する施設を対象として警備を行います。
施設の入口に立って不審者がいないかチェックしたり、館内を巡回したりするのが主な役割です。
また来訪者の応対や館内で発生したトラブルに対処することもあります。
守衛の役割は警備員の1号警備業務とほとんど同じですが、対象施設以外の警備業務を行うことはありません。
たとえば守衛が交通誘導を行ったり、誰かのボディガードになったりすることはないのです。
こうした点が警備員と守衛の大きな違いとなっています。
法律による規制が異なる
守衛と警備員には法律面の違いもみられます。
警備員は警備業法という法律で規制されており、業務や教育内容まで細かなルールが設けられています。
そのため、警備業法に違反してしまった時は、関係機関による改善指示などの処分を受ける可能性があります。
守衛は警備員とは異なるため、警備業法の規制を受けることはありません。
守衛と警備員の業務内容は似ていますが、守衛はあくまでも施設などに直接雇用されている従業員です。
立場上、施設の一業務として警備を行っているということから、警備業法の規制対象外となっています。
警備業法の欠格事由も適用対象外なので、該当者でも守衛になることはできます。
ただし、守衛の業務も知識や経験が求められます。
警備業法対象外だからと言って、警備員よりも仕事が簡単とは言えません。
研修にも違いがみられる
警備員と守衛の4つ目の違いが研修の有無です。
警備員には警備業法に基づいた研修(教育)が義務化されているため、所定の研修を受ける必要があります。
たとえば未経験者の場合は新任教育、現役の警備員については現任教育を受けなくてはいけません。
もし適切な研修を受けなかった場合は、警備業法違反とみなされる恐れがあります。
一方の守衛は法律によって義務化された研修がありません。
警備員のように、業務開始前または在籍中に新任・現任教育を受ける必要はないのです。
雇用主が研修・教育を実施するケースも見られますが、あくまで任意実施の研修となります。
警備員とは違い、法律で義務付けられているものではないのです。
そのため、雇用主が研修を実施しなかったとしても、法律で罰せられることはありません。
警備員とは?
警備員は警備業法で定められている役職のひとつで、さまざまな場所で警備業務に携わります。
配属先は多岐にわたりますが、個々のケースによって異なります。
警備員の主な仕事内容
警備員の主な仕事内容は、種類によって大きく変わります。
1~4号警備業務の具体的な役割は次のとおりです。
- 1号警備業務:施設の警備や出入管理、巡回やトラブルへの対処
- 2号警備業務:駐車場やイベント会場での交通誘導、歩行者の誘導および警備
- 3号警備業務:現金や貴重品の輸送・運搬時の警備
- 4号警備業務:対象者の身辺警護(ボディガード)および安全の確保
1号警備業務は、商業施設やビルなどの警備や巡回、トラブル対応が主な役割です。
関係者や業者などの出入りを監視したり、来訪に対応したりすることもあります。
2号警備業務は、駐車場・イベント会場など屋外で交通誘導にあたります。
来訪者が安全に利用できるように、周囲を監視しながら誘導や雑踏警備を行います。
3号警備業務は現金や貴重品の輸送警備で、運搬物の安全確保が主な仕事です。
4号警備業務はボディガードで、対象者を常に警護しながら不審者から守る役割を担います。
警備員の主な配属先(警備対象)
警備員の配属先・警護対象は次のとおりです。
- 1号警備業務:百貨店やショッピングセンター、オフィスビル、工場など
- 2号警備業務:工事現場や駐車場、イベント会場・施設など
- 3号警備業務:金融機関や貴重品を取り扱う施設など
- 4号警備業務:政治家や企業役員、芸能人、スポーツ選手など著名人
1号警備業務は百貨店などの施設が中心で、2号警備業務は工事現場やイベント会場で業務を遂行します。
3号警備業務は現金や貴重品の輸送警備にあたるため、それらを扱う施設を警備対象としています。
4号警備業務は政治家や芸能人などの著名人が主な警備対象です。
警備対象者の周囲について、決められた時間警備にあたります。
警備員になる方法は?
警備員を始めるためには警備会社の求人に応募し、採用される必要があります。
基本的に必要な資格はありませんので、応募条件を満たしていれば誰でもスタート可能です。
警備員に関する資格もありますが、警備員として働き始めた後でも取得できます。
ただし、欠格事由にあたる方は警備員になれません。
たとえば18歳未満の方や、禁固刑以上の刑を受けてから5年以内の方などが該当します。
他にもさまざまな欠格事由が規定されていますので、気になる方は確認をおすすめします。
守衛とは?
守衛は雇用主が運営する施設で警備などの業務にあたる職種のことです。
警備員とは違って業務対象・範囲が固定されています。
守衛の主な仕事内容
守衛の主な仕事内容は次のとおりです。
- 施設の警備および巡回
- 施設での来訪者の監視や応対
- 業者や関係者の応対
- 不審者や不審物の確認や対応
- 事故やトラブルなどへの対処
施設の警備や巡回の他、来訪者の監視や業者・関係者の応対も行います。
不審者・不審物を発見した際は適切に処理したり、トラブルの際には対処したりする業務もあります。
守衛の主な配属・勤務先
守衛の配属・勤務先は雇用主次第ですが、以下のような施設で勤務します。
- ショッピングセンターなど商業施設
- オフィスビル
- 学校
- 病院
- 公共施設
ショッピングセンターを始めとする商業施設や、オフィスビルで警護にあたるのが一般的です。
学校や病院、公共施設などで警備や来訪者の対応を行うケースもあります。
守衛の勤務先は多種多様ですが、警備員とは違って途中で変わるケースはほとんどありません。
通常は特定の施設へ常駐し、決められたシフトで業務に携わります。
守衛になる方法は?
守衛になるには、施設の運営会社などが募集している求人へ応募し、採用される必要があります。
欠格事由はないため、採用されれば誰でも働くことが可能です。
しかし守衛は勤務先が固定されるので、警備員のように多様なスキルを身に付けたり、経験を積んだりできません。
警備に関するスキルを磨きたい場合は警備員の仕事をおすすめします。
まとめ
守衛と警備員には、研修の有無や法律の規制などさまざまな違いがあります。
業務面では似ている部分もありますが、配属・勤務先や警備対象が異なるので注意が必要です。
守衛は施設の警備が中心で、警備員は他にも幅広い警備業務に携わります。
守衛は勤務先がほぼ固定である一方、警備員は配属先の選択肢が豊富です。