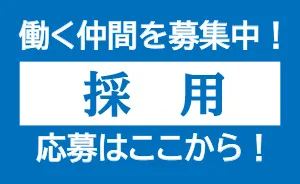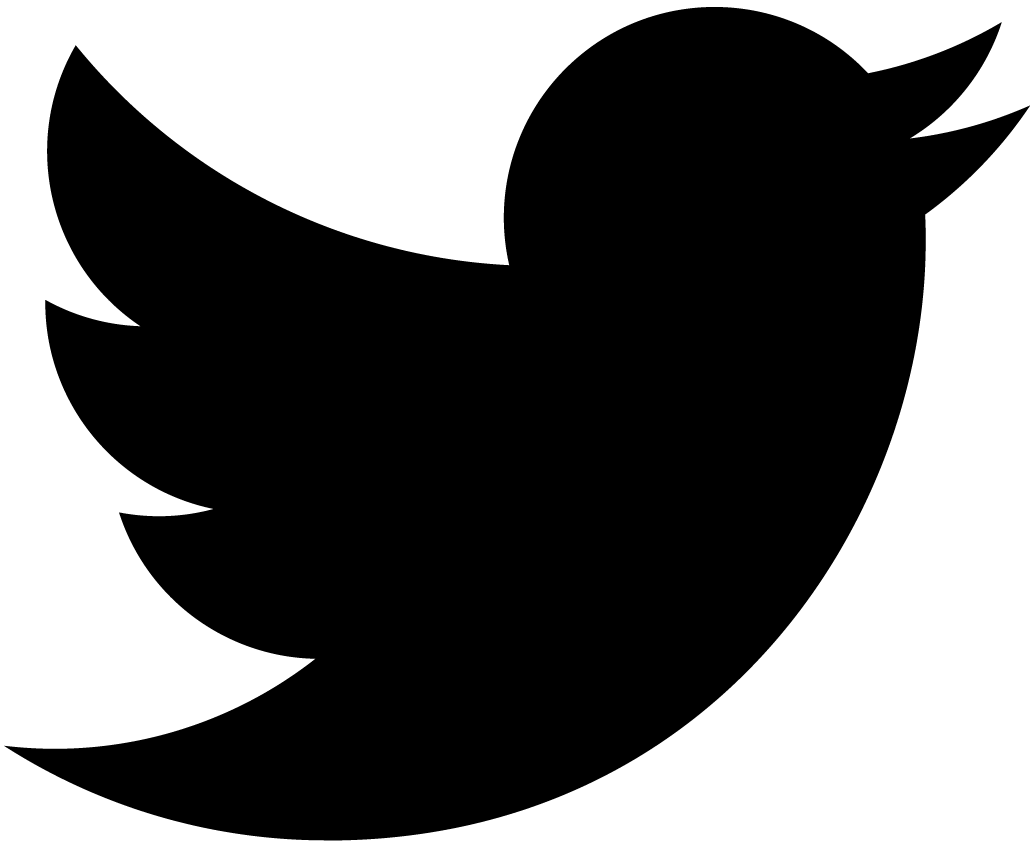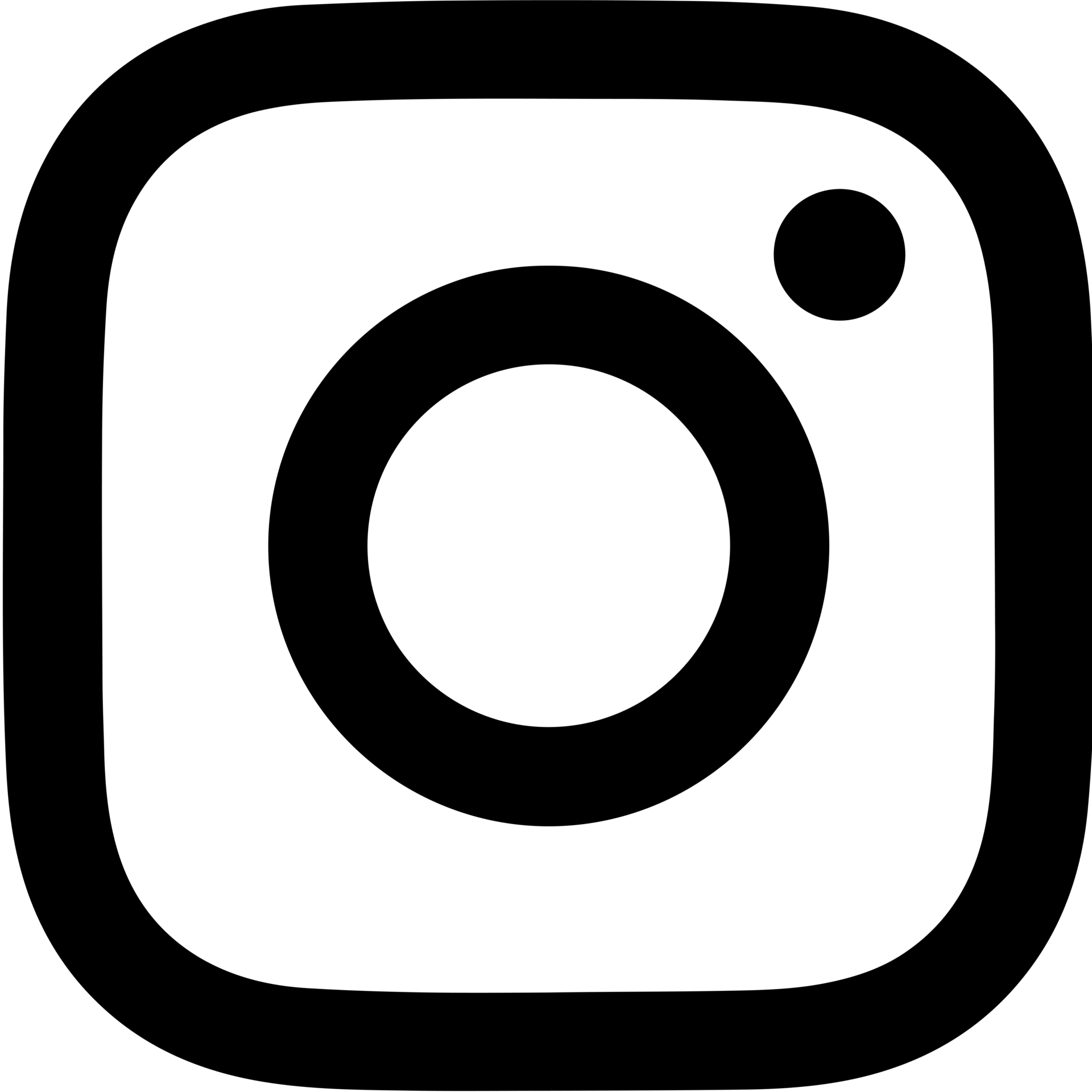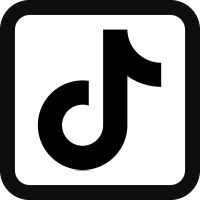警備業法の違反事例
2025.03.12 Wed
警備業法では、警備業に関する規制やルールが細かく定められています。
もし違反した時は罰則を課せられる可能性があるため、警備会社・警備員は同法を遵守する必要があります。
本記事では、警備業法の主な違反事例や罰則の他、違反が起こってしまう原因や理由も解説します。
警備業法の主な違反事例
警備業では、主に以下のような違反事例が見られます。
- 違法派遣
- 教育懈怠
- 教育実施の虚偽記録
それぞれ詳しく解説します。
警備員の違法派遣
警備業は基本的に請負契約で、警備員は指揮命令系統が警備会社にあります。
派遣は労働者派遣法で細かな規定があり、警備員の派遣は禁止されています。
違法派遣に当てはまるのが、適切な手順を踏まずに他社から警備員に応援に来てもらったケースです。
他社に警備員として応援に行った時も同様のケースに該当します。
もし上記に該当した場合は、警備業法違反で処分される可能性も否定できません。
警備員を派遣した会社はもちろん、依頼主が処分を受ける恐れがあります。
ただし、他社から警備員を呼ぶこと自体が違法になるわけではありません。
再委託など適切な手順を踏めば、警備員の応援を呼んだり応援に行ったりすることは可能です。
警備員の教育懈怠
教育懈怠(けいたい)とは、警備員に対して適切な教育を行わず、警備業務に従事させることを言います。
警備業法では警備員に対する教育についてルールを決めており、教育時間数も細かく規定されています。
例えば以下に該当する場合、教育懈怠とみなされる可能性があります。
- 新人に十分な教育を受けさせずに業務に従事させた
- 現任教育が必要な警備員に対する教育実施を忘れてしまった
- 警備業法で規定された教育時間に満たなかった
警備員に必要な教育時間は、新任教育と現任教育とで異なります。
ただ、いずれも年度ごとに最低教育時間が決まっています。
教育懈怠を避けるためには、教育時間の基準を満たすことが求められます。
もし教育懈怠とみなされた場合は、指示または営業停止処分となる恐れがあるため注意が必要です。
処分内容・期間は、警備業法に基づく教育を受けた警備員の割合によって異なります。
教育実施簿の内容の捏造
教育実施簿は警備業法第66条で定められた書類で、教育内容を細かく記載したものを言います。
警備業法では、警備会社が警備員に行った教育内容について教育実施簿への記録が義務化されています。
悪質な警備会社では教育実施簿を捏造する場合もあります。
たとえば警備員の教育が済んでいないにも関わらず、教育済みとして教育記録簿に虚偽記載するケースです。
警備会社は、通常1年に1回程度のペースで立入検査が行われます。
その際には教育実施簿の内容もチェックされますが、もし虚偽記載が発覚した場合は抜き打ち検査が行われることもあります。
教育実施簿の虚偽記載は警備業法違反であり、虚偽記載を行った原因に関わらず処分されます。
罰金が課せられる他、警備業の許可取り消し(認定証の返納命令)となる可能性もあります。
教育実施簿の捏造・虚偽記載に関する処分はかなり厳しく、営業停止処分で済むケースは多くありません。
大半は認定証の返納を命じられるなど、他の違反と比較しても処分が重くなっています。
その他の違反事例
上記で挙げた事例以外にも、次のような行為は警備業法に抵触する場合があるので注意が必要です。
- 業務上で知り得た情報を漏洩させた
- 警備の枠を超えた業務を遂行した(交通整理など)
- 欠格事由に該当する人物を警備員として働かせた
- 営業停止期間中または認定証返納後に警備業を行った
業務上の重要な情報を漏洩させた場合は、警備業法違反となることがあります。
交通整理など権限を超えた業務を遂行した時は、警備業法15条違反となる可能性も否定できません。
欠格事由にあたる人物が警備業務に従事した時も、警備業法違反となる恐れがあります。
もし警備員として働きたい方は、欠格事由に当てはまらないように注意が必要です。
他にも、営業停止期間中や認定証の返納後に警備業を行った場合も罰せられる可能性があります。
警備業法に違反した時の罰則は?
警備業法に違反した場合、状況に合わせた処分が課せられてしまいます。
罰則には複数の種類がありますが、違反内容によって処分の重さが大きく変わります。
研修実施などの指示
1つめの罰則の種類が「指示」です。
指示は警備業法におけるもっとも軽い罰則で、軽微な違反に対して課せられます。
悪質性がないと判断された時に下される処分ですが、主に以下のような指示が出されることがあります。
- 責任者に対する研修実施の指示
- 警備員に対する教育の指示
- 再発防止策の検討および報告の指示
違反内容次第ではあるものの、基本的に教育や研修、再発防止策の報告に関する指示などがほとんどです。
どのようなケースであっても、指示内容に従って対応すれば問題はありません。
指示内容に従わなかったり無視したりした時は、より重い処分が下される可能性もあります。
営業停止処分
2つめの罰則が「営業停止処分」です。
警備業法に違反した場合は、営業停止処分によって一定期間警備業を運営できなくなることがあります。
営業停止処分は相当に重い処分の一つですが、営業停止期間は違反内容によって大きく異なります。
たとえば7日ほどで済むこともあれば、30日程度の営業停止となるパターンもあります。
営業停止となるケースが多いのは、警備員の違法派遣や教育懈怠などです。
教育懈怠の場合、教育を受けていない警備員の割合によって営業停止期間が変わります。
しかし、教育を受けた警備員の割合が高い時は、教育実施に関する指示で済む可能性もあります。
警備業の許可取り消し(認定証の返納命令)
営業停止処分よりも重い罰則が、警備業に関する許可の取り消し(認定証の返納命令)です。
もし認定証の返納命令を受けると一定期間は警備業を営むことができなくなります。
認定証の返納命令は非常に重い処分ですが、決して珍しいものではありません。
警備業法の違反内容の悪質性次第では、営業停止処分を超えて認定証の返納命令が下される可能性もあります。
特に教育実施簿の捏造・虚偽記載については、認定証の返納命令となることも珍しくありません。
悪質性が高いと判断されますので、営業停止処分では留まらない可能性もあります。
罰金刑になるケースも
警備業法の違反内容次第では、罰金刑を課せられるので注意が必要です。
罰金刑の主な対象は教育実施簿の虚偽記載で、認定証の返納命令とは別に課せられることもあります。
指示に従わなかったり、営業停止中に警備業務を行ったりした時も注意が必要です。
行為の内容に関わらず、罰金刑になってしまう恐れがあります。
罰金そのものは決して高いと言えませんが、処分を下されたこと自体が問題となります。
仮に罰金を納めたとしても、警備会社としての信用が低下してしまう可能性があるのです。
いくつかある警備業法の罰則の中でも、認定証の返納命令と同等に重い処分と言えます。
なぜ警備業法の違反が起こるのか?
警備業法違反が起こる理由は、人手不足や業務負担の大きさなど様々です。
以下では、警備業法違反が発生する主な原因や理由を解説します。
警備員の人手不足によるもの
違法派遣の主な原因は警備員の人手不足です。
警備員数は警備会社によって異なるため、中には人手不足で悩まされているところもあります。
そのため、人手を確保するために他社から警備員に応援に来てもらう、というパターンは多々見られます。
しかし、警備員の派遣は禁じられているため、適切な手段を講じなくてはいけません。
もし適切なステップを踏まずに警備員の応援を呼んだ場合は、警備業法違反となってしまいます。
業務の負担が大きいため
もうひとつの理由は警備会社の業務負担の大きさです。
警備会社は警備員の管理から教育・訓練まで、多岐にわたる業務をこなします。
これらは警備業法で定められていますが、業務の負担は決して軽いものではありません。
その結果、警備員の教育が疎かになってしまうなど、警備業法に違反する行為が起きてしまうこともあります。
ただ、違反すると罰則が課せられるため、いかに業務負担を軽減するかが課題となります。
まとめ
警備業の適切な運営に欠かせない警備業法ですが、違反になってしまう事例は多岐にわたります。
もし違反すると指示や営業停止処分などが課せられる他、認定証の返納を命令されることもあります。
いずれにせよ、警備業法に違反しないよう業務を遂行することが大切です。